糖尿病・喫煙・骨粗しょう症の薬…インプラント治療への影響と、安全に進めるための条件を解説

こんにちは。三重県鈴鹿市の大木歯科医院 院長の笠井 啓次です。
インプラント治療は、失った歯の機能と見た目を劇的に回復させる、非常に優れた治療法として確立されました。当院にも、この治療を希望されて、多くの方がご相談に来られます。その際、手術そのものの内容と合わせて、私たちが非常に重要視し、患者様にも必ずお伺いするのが、「現在治療中のご病気や、日常的な習慣、服用されているお薬」についてです。
特に、患者様から「糖尿病の持病があるのですが、手術は可能ですか?」「長年タバコを吸っていますが、大丈夫でしょうか?」「骨粗しょう症の薬を飲んでいると、インプラントはできないと聞いたのですが…」といったご質問をいただくことは、決して少なくありません。
インプラント治療は、顎の骨に人工歯根を埋め込む外科手術です。その成功は、お口の中の状態だけでなく、患者様の全身の健康状態と密接に、そして深刻に関わっています。これらの全身状態や生活習慣を正しく把握せずに治療を進めることは、重大なリスクを伴います。今回は、インプラント治療を安全に受けていただくために、特に注意が必要な「糖尿病」「喫煙」「服薬(骨粗しょう症の薬など)」という3つの要因が、治療にどのような影響を与えるのか、そして、治療を受けるための条件について、詳しく解説していきます。
目次
- 【糖尿病】なぜ血糖コントロールが重要?インプラント治療の絶対条件
- 【喫煙】インプラントの“天敵”。ニコチンが引き起こす致命的なリスク
- 【服薬①】最重要:骨粗しょう症の薬(BP製剤など)と顎骨壊死のリスク
- 【服薬②】血液サラサラの薬(抗凝固薬・抗血小板薬)を飲んでいる場合
- 安全な治療への鍵は「医科歯科連携」と「正確な申告」
- まとめ
1. 【糖尿病】なぜ血糖コントロールが重要?インプラント治療の絶対条件
糖尿病は、今や国民病とも言えるほど多くの方が罹患されている病気ですが、インプラント治療においては、特に厳重な管理が必要となる疾患の一つです。かつては「糖尿病患者様へのインプラントは禁忌」とされていた時代もありましたが、現在は、**「血糖値が良好にコントロールされていれば、治療は十分に可能」**というのが共通認識です。
なぜ、血糖コントロールがそれほど重要なのでしょうか。それは、高血糖の状態が続くと、主に2つの大きな問題がインプラント治療の成功を妨げるからです。
- 易感染性(いかんせんせい):血糖値が高いと、細菌と戦う白血球の機能が低下し、体全体の免疫力が落ちてしまいます。インプラントは外科手術ですので、術後に傷口が細菌に感染するリスクはゼロではありません。糖尿病の方は、この術後感染のリスクが健康な方に比べて格段に高く、一度感染すると炎症が重症化しやすい傾向があります。
- 創傷治癒能力の低下(傷が治りにくい):高血糖は、全身の毛細血管にダメージを与え、血流を悪化させます。インプラント治療の成功は、手術で埋め込んだインプラントと顎の骨がしっかりと結合すること(オッセオインテグレーション)にかかっています。しかし、血流が悪化すると、傷を治すために必要な酸素や栄養素が手術部位に十分に行き渡らず、傷の治りが遅れたり、インプラントと骨がうまく結合しない「インテグレーション不全」という、治療失敗のリスクが高まります。
では、「コントロール良好」とは、具体的にどのくらいの数値を目安にするのでしょうか。私たちは、過去1~2ヶ月の血糖値の平均を反映する「HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)」の値を、最も重要な指標としています。一般的に、HbA1cが7.0%未満で安定していることが、インプラント治療を受けるための望ましい条件となります。もちろん、この判断は、患者様の糖尿病を管理されている主治医(内科医)の先生との緊密な連携(医科歯科連携)のもとで、総合的に行います。治療後も、インプラントの歯周病である「インプラント周囲炎」のリスクが健康な方より高いため、継続した血糖コントロールと、通常より頻繁な歯科メンテナンスが、生涯にわたって必要不可欠です。
2. 【喫煙】インプラントの“天敵”。ニコチンが引き起こす致命的なリスク
糖尿病と並んで、あるいはそれ以上に、インプラント治療の成功率を著しく低下させることが、科学的に明らかになっている要因。それが「喫煙」です。私たちは、インプラント治療を希望される喫煙者の患者様には、その深刻なリスクについて、非常に厳しくお伝えしています。
タバコに含まれるニコチンには、血管を強力に収縮させる作用があります。喫煙をすると、お口の中の歯茎の毛細血管が縮こまり、手術部位への血流が著しく低下してしまいます。これは、インプラント治療にとって、まさに致命的な影響を与えます。 前述の糖尿病と同様に、血流が悪化することで、「創傷治癒能力の低下」と「易感染性」という二重のリスクが発生します。手術した傷が治りにくく、骨との結合が妨げられるリスク(初期固定の失敗)が、非喫煙者に比べて何倍にも跳ね上がります。データによっては、喫煙者のインプラント失敗率は、非喫煙者の2~3倍にもなるという報告があるほどです。
さらに深刻なのは、治療が成功した「後」のリスクです。喫煙は、インプラントの歯周病である「インプラント周囲炎」の最大の危険因子です。 ニコチンの影響で歯茎の血流が悪くなると、細菌に対する抵抗力が低下し、感染が起こりやすくなります。加えて、喫煙者の歯茎は、炎症のサインである「出血」が起こりにくいという特徴があります。そのため、インプラント周囲炎が発症しても自覚症状が出にくく、水面下で静かに進行し、気づいた時にはインプラントを支える骨が広範囲に溶けてしまっている、というケースが非常に多いのです。
これらの深刻なリスクを回避するため、私たち歯科医師が患者様にお願いする最低限の条件は、「手術の2週間以上前から、手術後インプラントが骨と結合するまでの約2~3ヶ月間の、一時的な禁煙」です。しかし、これはあくまで治療を成功させるための最低ラインです。インプラントを10年、20年と長持ちさせるためには、治療を機に、完全な禁煙(卒煙)に踏み切っていただくことを、心の底から強くお勧めします。
3. 【服薬①】最重要:骨粗しょう症の薬(BP製剤など)と顎骨壊死のリスク
現在服用されているお薬の中で、インプラント治療(特に抜歯などの外科処置)において、最も注意が必要なのが、骨粗しょう症(こつそしょうしょう)の治療薬の一部です。特に「BP製剤(ビスフォスフォネート製剤)」と呼ばれる種類のお薬を、長期間、注射あるいは経口(飲み薬)で使用されている方は、特別な注意が必要です。
BP製剤は、骨が吸収されるのを抑える非常に優れたお薬ですが、その強力な作用が、逆に、顎の骨の代謝や治癒能力を極端に低下させてしまうことがあります。その結果、インプラント手術や抜歯といった、顎の骨に刺激が加わる処置をきっかけに、手術した部分の骨が感染を起こし、骨が腐ってしまう「顎骨壊死(がっこつえし)」という、非常に治りにくい重篤な副作用を引き起こすリスクがあることが報告されています。
「骨粗しょう症の薬を飲んでいると、絶対にインプラントはできない」というわけではありません。リスクの度合いは、BP製剤の使用期間(特に3~4年以上継続しているか)、投与方法(注射薬か、飲み薬か。注射薬の方がリスクは高いとされます)、他の薬剤(ステロイドなど)との併用の有無などによって、大きく異なります。
私たちがインプラント治療の前に、必ず骨粗しょう症の治療歴についてお伺いするのは、このリスクを把握するためです。もし該当するお薬を服用されている場合は、必ず、そのお薬を処方している主治医(整形外科医や内科医など)に対診を行い、インプラント治療を行っても安全か、あるいは、一時的にお薬を休薬(きゅうやく)する必要があるかなどを、慎重に協議します。患者様の自己判断での休薬は、骨折のリスクを高めるなど非常に危険ですので、絶対にやめてください。安全が確認できない限り、私たちは外科処置に進むことはありません。
4. 【服薬②】血液サラサラの薬(抗凝固薬・抗血小板薬)を飲んでいる場合
脳梗塞や心筋梗塞の既往がある方、あるいはその予防のために、血液をサラサラにするお薬(抗凝固薬:ワーファリンなど、抗血小板薬:バイアスピリン、プラビックスなど)を服用されている方も、非常に多くいらっしゃいます。
これらのお薬を服用されている場合、インプラント手術中に、血が止まりにくくなる「出血リスク」が高まります。 「手術だから、事前に薬を止めてこないといけないのでは?」と心配される患者様もいらっしゃいますが、絶対に自己判断で服用を中止しないでください。 お薬を止めることによって、血栓(血の塊)ができて、脳梗塞や心筋梗塞を再発してしまうリスクの方が、手術の出血リスクよりも、はるかに重大で、命に関わる問題だからです。
現在では、多くの場合、お薬を継続したままでも、安全にインプラント手術を行うことが可能です。私たち歯科医師は、出血が起こりやすいことを前提として、手術範囲を最小限にとどめたり、止血剤を確実に使用したり、縫合(傷口を縫うこと)をより厳密に行ったりと、万全の止血処置を準備して手術に臨みます。もちろん、この場合も、お薬を処方されている主治医(循環器内科医など)との連携は不可欠です。手術の可否や、お薬の調整が必要かどうかは、必ず主治医の先生の指示を仰ぎます。
5. 安全な治療への鍵は「医科歯科連携」と「正確な申告」
ここまで、糖尿病、喫煙、服薬という3つの大きな要因についてお話ししてきましたが、全てのケースに共通する、安全なインプラント治療のための絶対的な鍵が二つあります。
一つは、「医科歯科連携」です。糖尿病の内科医、骨粗しょう症の整形外科医、心疾患の循環器内科医…患者様の全身状態を管理されている主治医の先生方と、私たち歯科医師が、紹介状や対診を通じて、患者様の情報を正確に共有し、治療方針について緊密に連携すること。これが、安全を担保する上で何よりも重要です。
そして、もう一つ、それ以上に大切なのが、「患者様ご自身による、正確な情報提供」です。 初診時の問診票にお答えいただく際、「これは歯科治療には関係ないだろう」と自己判断せず、
- 現在治療中の全ての病名(高血圧、肝炎、アレルギーなども含む)
- 現在服用中の全てのお薬(サプリメントも含む。お薬手帳のご持参が確実です)
- 過去の大きな病気や手術の経歴
- 喫煙や飲酒などの生活習慣
これらを、包み隠さず、正確に私たちに申告していただくこと。これが、私たち医療者が、起こりうるリスクを事前に察知し、万全の準備を整えるための、唯一の、そして最大の情報源となります。「言い忘れていた」が、重大な医療事故に繋がる可能性もあるのです。
6. まとめ
インプラント治療は、素晴らしい結果をもたらす可能性のある治療ですが、それは、患者様のお体の安全が、100%確保されて初めて成り立つものです。
- 糖尿病は、血糖コントロールが良好(HbA1c 7.0%未満目安)であれば治療可能。内科医との連携が必須。
- 喫煙は、インプラントの成功率を著しく下げる最大の敵。最低でも手術前後の禁煙、できれば完全な卒煙が強く推奨される。
- 骨粗しょう症の薬(特にBP製剤)は、顎骨壊死のリスクがあるため、主治医への確認が絶対に必要。
- 血液サラサラの薬は、自己判断で止めず、継続したまま安全に手術を行う方法を、主治医と歯科医師が協議する。
- 最も大切なのは、患者様ご自身が、ご自身の全身状態やお薬の情報を、正確に歯科医師に伝えること。
私たち大木歯科医院は、インプラント治療に関する豊富な経験と知識を持つだけでなく、地域の医療機関とも密接に連携し、患者様の全身の安全を第一に考えた治療計画を立案します。持病や生活習慣のことで、インプラント治療に不安を感じていらっしゃる方は、どうかお一人で悩まず、まずはその不安の全てを、私たちにご相談ください。
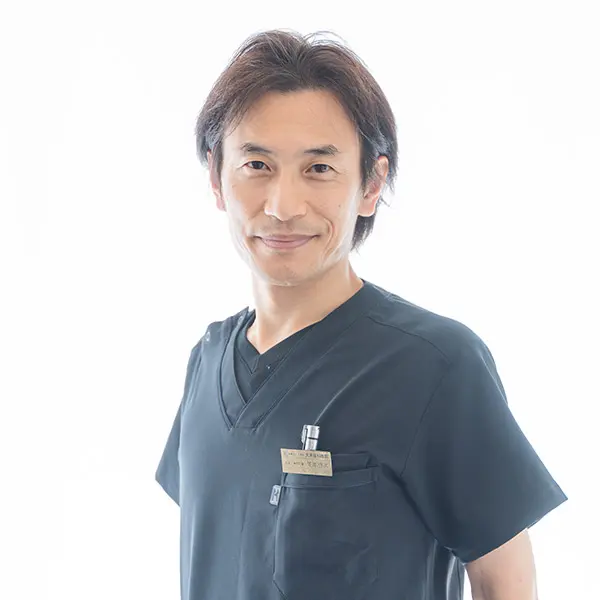
略歴
- 国立徳島大学歯学部卒業
- American Academy of Implant Dentistry
- Associate Fellow
- Astra tech implant インストラクター
- Osstem implant インストラクター
- 歯科医師臨床研修指導歯科医
資格・所属学会
- アメリカインプラント学会(AAID)
- 日本口腔インプラント学会
- 日本審美歯科学会
- 日本臨床歯周病学会
- 日本小児歯科学会
- 東京SJCD会員
一人ひとりの多様なニーズにお応えします
当院は難しい症例を含む多くの症例を経験しており、患者様の理想通りの治療をご提供できるよう、チーム一丸となって取り組んでいます。
![鈴鹿市の歯医者・歯科医院 [大木歯科医院]](https://www.ohki-dental.com/wp-content/uploads/2018/10/logo.png)
