インプラント最大の敵「インプラント周囲炎」とは?その恐ろしさと、歯科医が教える最強の予防法
こんにちは。三重県鈴鹿市の大木歯科医院 院長の笠井 啓次です。
インプラント治療は、失った歯の機能と見た目を、まるでご自身の歯のように回復できる素晴らしい治療法です。当院でも、治療を終えられた患者様が、何でも美味しく食べられるようになったと、心からの笑顔を見せてくださることに、日々やりがいを感じています。しかし、インプラント治療は、「入れたら終わり」ではありません。治療が成功した後、そのインプラントを長期間、健康に維持していくためには、患者様ご自身に、そして私たち医療従事者に、非常に重要な責務が生まれます。
先日、まさにインプラント治療を終えられた患者様から、このようなご質問をいただきました。「インプラントも、歯周病のような病気になると聞きました。具体的には、どのような病気なのでしょうか?どうすれば防げますか?」
これは、インプラント治療後の未来を考える上で、最も重要なご質問です。インプラントの最大の敵、それは「インプラント周囲炎」と呼ばれる病気です。今回は、このインプラント周囲炎とは一体何なのか、なぜ天然歯の歯周病よりも恐ろしいのか、そして、その大切なインプラントを守るための、最も確実な予防法について、詳しく解説していきます。
当院のインプラントページはこちらから→インプラント治療
目次
- 「インプラント周囲炎」とは?天然歯の歯周病との決定的な違い
- なぜ怖い?インプラント周囲炎が「サイレント・キラー」と呼ばれる理由
- 予防法①:ご自宅での徹底したセルフケア(インプラントの清掃法)
- 予防法②:歯科医院での「プロフェッショナル・メンテナンス」の絶対的な必要性
- もし、インプラント周囲炎になってしまったら?その治療法と限界
- まとめ
1. 「インプラント周囲炎」とは?天然歯の歯周病との決定的な違い
インプラント周囲炎は、その名の通り、インプラントの周りの組織(歯茎や骨)が炎症を起こす病気です。原因は、天然歯の歯周病と全く同じで、お口の中の細菌、特に歯垢(プラーク)の磨き残しです。プラークの中の細菌が毒素を出し、まずはインプラントの周りの歯茎が炎症を起こします(これを「インプラント周囲粘膜炎」と言います)。この段階であれば、まだ引き返すことが可能です。しかし、これが進行すると、炎症はインプラントを支えている顎の骨にまで達し、その骨を溶かしてしまいます。 これが「インプラント周囲炎」です。
「なんだ、歯周病と同じじゃないか」と思われるかもしれません。しかし、インプラントは、天然の歯と比べて、この細菌感染に対する「防御力」が決定的に弱いのです。
天然の歯は、「歯根(しこん)」と「顎の骨」の間に、「歯根膜(しこんまく)」という、厚さ0.2mmほどの薄いクッションのような組織があります。この歯根膜には、非常に豊富な血管が通っており、細菌が侵入しようとすると、この血管を通って、白血球などの免疫細胞が駆けつけ、細菌と戦ってくれる、強力な「防御システム」が備わっています。
一方、インプラントは、チタン製の人工歯根が、顎の骨と直接、強固に結合しています(オッセオインテグレーション)。ここには歯根膜が存在しません。 つまり、細菌の侵入に対する、この強力な防御システムが存在しないのです。そのため、一度インプラントの奥深くに細菌が侵入すると、免疫細胞が十分に届かず、炎症は、いとも簡単に、そして急速に、インプラントを支える骨へと到達してしまいます。これが、インプラント周囲炎が、天然歯の歯周病よりもはるかに恐ろしいと言われる、最大の理由です。
2. なぜ怖い?インプラント周囲炎が「サイレント・キラー」と呼ばれる理由
インプラント周囲炎の、もう一つの恐ろしい特徴は、「自覚症状がほとんどないまま、急速に進行する」ことです。歯科医師の間では、「サイレント・キラー(静かなる殺し屋)」と呼ばれるほど、非常に厄介な病気です。
天然歯であれば、歯周病が進行すると、歯根膜が炎症を起こし、「歯が浮いたような感じがする」「噛むと痛い」といった違和感や、痛みを比較的早期に感じることがあります。これは、体からの「異常事態だ!」という警告サイン(アラーム)です。
しかし、インプラントには、このアラームを鳴らしてくれる歯根膜がありません。また、インプラント自体に神経も通っていません。そのため、インプラント周囲炎が発症し、水面下で骨がどんどん溶けていっても、痛みや違和感といった自覚症状が、ほとんど現れないのです。 患者様が気づく可能性のある初期症状は、「歯磨きの時に、歯茎から少し血が出る」程度かもしれません。しかし、これは天然歯でもよくあることと、見過ごされてしまいがちです。そして、 「なんだか歯茎が腫れぼったい」 「歯茎を押すと、嫌な臭いのする膿(うみ)が出てきた」 「インプラントが、少しグラグラする気がする」 といった、明らかな自覚症状が出た時には、すでにインプラントを支える骨の大部分が失われ、手遅れ(抜インプラント)一歩手前となっているケースが、非常に多いのです。症状がないまま静かに進行し、気づいた時には致命傷になっている。これが、インプラント周囲炎の最大の恐ろしさです。
3. 予防法①:ご自宅での徹底したセルフケア(インプラントの清掃法)
では、この恐ろしいインプラント周囲炎を防ぐためには、どうすれば良いのでしょうか。その答えは、「原因となる細菌(プラーク)を、徹底的に除去し続ける」、これに尽きます。その第一歩が、患者様ご自身による、毎日の「セルフケア」です。インプラント治療を受けた方は、天然歯だけの時以上に、丁寧で、精密な歯磨きが求められます。
- 歯ブラシ(基本の清掃): 歯ブラシの毛先を、インプラントの被せ物と歯茎との境目に、45度の角度で正確に当て、小刻みに振動させるように優しく磨きます。インプラントの構造上、被せ物の根元は、天然歯よりも少し細く、段差になっていることがあります。この「境目」こそが、プラークが最も溜まりやすい「魔の三角地帯」です。ここを徹底的に狙って磨く意識が重要です。ゴシゴシと力を入れすぎると、逆に歯茎を傷つけてしまうため、注意しましょう。
- 歯間ブラシ(最重要アイテム): インプラントケアの主役と言っても過言ではありません。インプラントと隣の歯との間は、歯ブラシの毛先が絶対に届かない領域です。この隙間に、ご自身の隙間のサイズに合った「歯間ブラシ」を挿入し、前後に数回動かして、側面の汚れを掻き出します。特に奥歯のインプラントには必須です。
- タフトブラシ(ワンタフトブラシ): 毛先が小さく、鉛筆のように尖った形の、仕上げ磨き用の歯ブラシです。歯ブラシが届きにくい、インプラントの被せ物の根元(歯茎との境目)を、ぐるりとなぞるように磨いたり、一番奥のインプラントの後ろ側を磨いたりするのに、絶大な威力を発揮します。
- デンタルフロス(糸ようじ): インプラントが2本以上連結してブリッジになっている場合など、歯間ブラシが通らない構造の場合は、「スーパーフロス」と呼ばれる、先端が硬くなった特殊なフロスを、橋の下に通して清掃する必要があります。
インプラントのセルフケアは、「歯ブラシだけで終わり」では、絶対に不十分です。歯ブラシに加えて、「歯間ブラシ」や「タフトブラシ」を必ず併用し、立体的に清掃する技術を習得していただく必要があります。私たち歯科衛生士が、あなたのお口の状態に合わせて、最適な器具と、その具体的な使い方を、責任を持ってご指導させていただきます。
4. 予防法②:歯科医院での「プロフェッショナル・メンテナンス」の絶対的な必要性
セルフケアが、インプラントを守る「盾」だとすれば、歯科医院での定期メンテナンスは、その盾では防ぎきれない攻撃を排除し、盾そのものを修理・強化するための「城壁」です。セルフケアをどれだけ完璧に行っているつもりでも、インプラント周囲炎の予防は、セルフケアだけでは絶対に達成できません。 なぜなら、磨き残したプラークは、やがて「バイオフィルム」という、細菌が強固なバリアを張ったヌルヌルの膜になり、さらには「歯石」という硬い石になって、ご自身の歯磨きでは絶対に除去できなくなるからです。
歯科医院での定期メンテナンス(プロフェッショナルケア)は、このご自身ではコントロールできないレベルの汚れを、専門的な器具と技術で徹底的に破壊・除去するための、必要不可欠なプロセスなのです。 そして、それ以上に重要なのが、インプラント周囲炎が発症していないかを、プロの目で厳しくチェックする「定期検診」の役割です。
【定期メンテナンスの主な内容】
- ①歯茎のチェック:インプラント周囲の歯茎に、炎症、出血、腫れがないか、歯周ポケットの深さは正常かを、専用の器具で優しく測定します。初期の炎症(周囲粘膜炎)をいち早く察知します。
- ②インプラントの状態チェック:インプラント本体にグラつき(動揺)がないか、被せ物(上部構造)に欠けや緩みがないか、被せ物とインプラントを連結しているネジ(スクリュー)に緩みがないかを確認します。
- ③レントゲン撮影による骨レベルの確認:年に1回程度、レントゲンを撮影し、インプラント周囲炎の最大のサインである「骨の吸収(骨が溶けていないか)」を、目に見えない部分まで精密に確認します。これこそが、自覚症状のないインプラント周囲炎を早期発見する、唯一にして最強の方法です。
- ④専門的なクリーニング(PMTC):インプラントのチタン表面を傷つけないよう、プラスチック製やカーボン製の専用器具、あるいは専用のパウダー(エアフロー)を用いて、歯ブラシでは落とせないバイオフィルムや歯石を徹底的に除去します。
- ⑤噛み合わせのチェックと調整:インプラントには歯根膜がないため、噛み合わせの力が強すぎると(過重負担)、インプラントや骨にダメージを与え、骨吸収の原因となることがあります。定期的に噛み合わせをチェックし、必要であれば微調整を行います。
このプロフェッショナル・メンテナンスを、お口のリスク(歯周病の既往、喫煙、清掃状態など)に応じて、3ヶ月~半年に1回、必ず受けていただくこと。これが、インプラントを長持ちさせるための、患者様と私たちとの、何よりも大切なお約束となります。
5. もし、インプラント周囲炎になってしまったら?その治療法と限界
ご質問にあった、「もし、なってしまったら、治療はできるのか?」という点についてお話しします。答えは、「早期発見であれば、治療は可能です。しかし、進行してしまった場合の治療は、非常に困難を極めます」となります。
- ステージ1:インプラント周囲粘膜炎(歯茎だけの炎症) この初期段階であれば、治療はまだ間に合います。歯科医院での徹底したクリーニングと、患者様ご自身によるセルフケアの劇的な改善によって、歯周病菌の数をコントロールできれば、炎症は治まり、健康な歯茎に戻ることが可能です。
- ステージ2:インプラント周囲炎(骨まで進行) 一度、骨が溶けてしまった場合、その治療は非常に難しくなります。
- 軽度~中等度:麻酔をして、歯茎の奥深く、インプラントの表面にこびりついた細菌の塊や汚染物質を、専用の器具を使って徹底的に掻き出す「デブライドメント」という処置を行います。
- 重度:デブライドメントだけでは改善が難しく、歯茎をメスで切開して、インプラントの表面を直接目で見て洗浄する外科的な処置(フラップ手術)が必要になります。インプラントの表面は、天然歯の根と違って複雑な凹凸があり、そこに付着した細菌を完全に除去(デコンタミネーション)するのは、至難の業です。場合によっては、失われた骨を再生させるための「骨造成」を試みることもありますが、その成功率は決して高くはありません。
そして、ご質問の「最悪の場合」についてです。 重度のインプラント周囲炎によって、インプラントを支える骨がほとんど失われてしまい、インプラントが大きく揺れて、痛みや腫れを繰り返すような状態になった場合。あるいは、周りの健康な歯にまで悪影響を及ぼすと判断された場合には、周囲の組織を守るために、そのインプラントを撤去する(抜く)という、苦渋の決断を下さざるを得ません。
せっかく時間と費用をかけて手に入れたインプラントを、再び失ってしまう。これは、患者様にとっても、私たち医療者にとっても、最も避けたい、最悪の結末です。この結末を避けるために、私たちは、口を酸っぱくして「予防」の重要性をお話ししているのです。
6. まとめ
インプラントを失う最大の原因、「インプラント周囲炎」。その真実と、向き合い方について、ご理解いただけましたでしょうか。
- インプラント周囲炎は、細菌による感染症だが、天然歯の歯周病と違い「防御システム(歯根膜)」がないため、進行が速い。
- 「痛み」などの自覚症状がほとんど出ないまま進行し、気づいた時には手遅れになりがちな、「サイレント・キラー」である。
- この病気を防ぐ唯一の方法は、「予防」しかない。
- 予防には、患者様ご自身による日々のセルフケア(歯間ブラシ、タフトブラシの併用)が不可欠。
- そして、それ以上に、歯科医院での定期的なプロフェッショナル・メンテナンス(骨のチェック、専門的清掃)が、その寿命を決定づける鍵となる。
インプラントは、あなたのお口の中で、素晴らしい機能を発揮してくれる、頼もしいパートナーです。しかし、それは同時に、あなたが愛情を持って、日々ケアをしてあげなければ、すぐに健康を損ねてしまう、繊細な存在でもあります。そのことを決して忘れず、私たち専門家と、固いパートナーシップを組んで、一緒にあなたの大切なインプラントを、生涯にわたって守り育てていきましょう。三重県鈴鹿市の大木歯科医院では、インプラント治療後のメンテナンスに、特に力を入れて取り組んでいます。
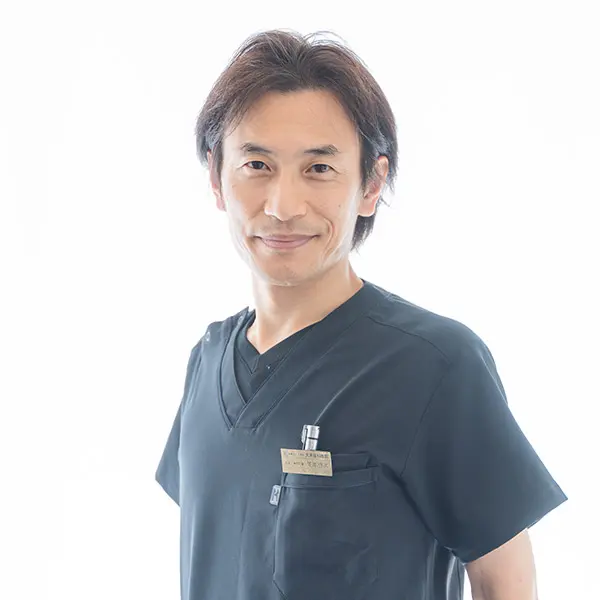
略歴
- 国立徳島大学歯学部卒業
- American Academy of Implant Dentistry
- Associate Fellow
- Astra tech implant インストラクター
- Osstem implant インストラクター
- 歯科医師臨床研修指導歯科医
資格・所属学会
- アメリカインプラント学会(AAID)
- 日本口腔インプラント学会
- 日本審美歯科学会
- 日本臨床歯周病学会
- 日本小児歯科学会
- 東京SJCD会員
一人ひとりの多様なニーズにお応えします
当院は難しい症例を含む多くの症例を経験しており、患者様の理想通りの治療をご提供できるよう、チーム一丸となって取り組んでいます。
![鈴鹿市の歯医者・歯科医院 [大木歯科医院]](https://www.ohki-dental.com/wp-content/uploads/2018/10/logo.png)
